よく晴れた2013年4月12日午前10時、僕は代官山蔦屋書店で『色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年』を手に取った。小説コーナーに平積みにされたその本を購入し、併設されたスターバックスではなく、2階のAnjinに入った。平日の午前中のAnjinは人影もまばらで、ゆっくり小説を読むには最適な場所に思えた。800円のアイスコーヒーを頼み、僕は1ページ目を捲った。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は、そのタイトルのわりに、表紙がカラフルだった。色彩のない世界の物語を想像していたが、拍子抜けだった。
名古屋の高校の同級生の仲良し男女5人組という設定から派生された物語だった。主人公の多崎つくる以外は皆、各々の名前に色が入っている。赤、青、シロ、クロ。相対的に多崎つくるだけを色を持っていなかった。しかし、田崎ではなく「多崎」とした点に、何か意味合いを感じた。高校卒業後に多崎だけが上京し、20歳の時に他のメンバーから5人組として付き合えなくなったことを通告される。多崎は彼彼女らとの日々を失い、色を失い、半年ほど精神的に生死を彷徨う。いつしか36歳にになっており、昔から好きだった駅を「つくる」仕事に就き、恵比寿で38歳の旅行関係の仕事に務める女性とBARで酒を飲んでいる。
その辺りまで読んで一息つき、今日はこれからどうしようかと考え、メールした女性と昼食を共にすることにした。彼女は朝のテレビでこの小説がニュースになっていたことを僕に教えてくれ、表紙がわりと色彩豊かであることを知っていた。その後天気が良かったので目黒まで自転車で赴き、地下にある昔ながらの喫茶店で続きを読み始めた。村上春樹の作品の主人公には一貫性がある。主人公の口癖、思考回路、あるいはリズム。しかし、多崎つくるには村上春樹作品の主人公らしさが見受けられなかった。「色彩を持たない」とは村上春樹作品の主人公としての色彩、という意味も帯びていたのだろうか。
20歳以来会っていない他の4人に会う必要があると38歳の女にそそのかされ、他の4人に会いに行き、20歳の時にあった出来事を暴く。それが巡礼だ。彼にとっての36歳が巡礼の年ということになる。その中で人が死んでいた、あるいは性的な何かがあった。その辺は常套句のように登場する。ヘルシンキという「ここではないどこか」もいつも通り登場する。骨格はいつもの村上春樹通りだ。しかし、多崎つくるには「やれやれ」もなければ「悪くない」もない。
村上春樹作品にしては非常に珍しいのが「5人組」という設定だ。村上春樹の長編小説は往々にして男女の二項対立を取るパターンが見受けられる。今回は370ページということもあり、長編ではなく中編小説といえなくもない。5人組という設定、そして一人を失うという設定はオレンジデイズに似ていると感じた。5人組的なグループ交際を中心とした物語は、色恋沙汰がなさそうな平和なグループであるかのように見せかけて、最後の方には必ず何かが起きる。お決まりのパターンだ。グループ交際を描きたい時は、友情の大切さも描きたい気分なのであろうか。
村上春樹小説の主人公的な色彩を持たない多崎つくるは、そのニュートラルさ、あるいはそのやる気のなさといった無色さは身に纏っていた。ある意味では飄々としていた。色のないところはそのまま残したのであろう。
目黒の喫茶店を経て、恵比寿ガーデンプレイスのスターバックスに移り、自宅で僕は『色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年』を読み終えた。初速こそネームバリューで売れるだろうが、あまり売れない本になるだろうなと感じた。村上春樹的な奥深さや、思考する余地があまり残されていない作品に思えた。深くはない。あるいはその村上春樹らしくなさに、興味を持つ人もいるかもしれない。
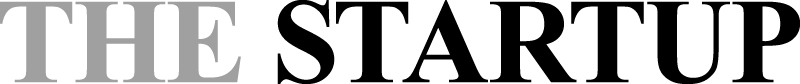




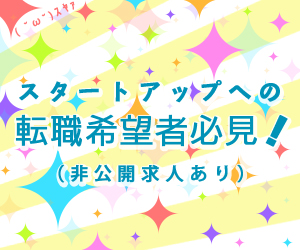





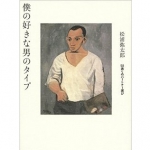
![CoffeeMeeting[コーヒーミーティング]](http://coffeemeeting.jp/assets/logo_circle.png)